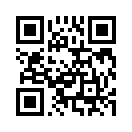2006年10月22日
元ひめゆり学徒と若者たちの500日
とゆうのは、この本のサブタイトルであります。
平和は「退屈」ですか 下嶋哲朗 岩波書店
帯には、こんなことが書いてある。
「戦争?したっていいじゃん」
―ある高校生が言った
「私たちがいなくなったあと、誰が私たちを語るのでしょうか」
―あせりをつのらせる ひめゆりの女性たち
平和は「退屈」ですか 下嶋哲朗 岩波書店
帯には、こんなことが書いてある。
「戦争?したっていいじゃん」
―ある高校生が言った
「私たちがいなくなったあと、誰が私たちを語るのでしょうか」
―あせりをつのらせる ひめゆりの女性たち
「戦争体験のない者が、戦争体験のない者を相手に、戦争体験を語る」
ひめゆりの人たちと、沖縄の高校生・大学生たちが、
一緒にこのテーマに取り組んだ「虹の会」の活動を紹介した本です。
色々な示唆に富んでいて、とても面白かった。
まず、平和学習について。
沖縄では小学生から高校生まで、6月23日の前になると、
平和学習という授業が行われるそうです。
沖縄戦の被害を語る講演やビデオを見て、その感想文を書くという内容が定番。
この平和学習は、小学校2年生から高校生まで、
ずっと同じレベルの学習をするのと同じようなものだ、
という指摘が、若者からありました。
算数なら、足し算、引き算、からどんどんレベルアップしていくのに、
平和学習でやることは、ずっと計算問題ばかり、というのと同じだというんですね。
確かに、「平和学習」の感想文で、「正解」として求められているのは、
「戦争は悲惨です。今日は命の大切さと平和の大切さを感じました。二度と戦争を起こしてはいけません」
という内容ですわな。
かく言う私も、小学校、中学校と、原爆のことを勉強するたびに、
「戦争は悲惨です。特に原爆は、罪もない人を簡単に殺し、後遺症で苦しめる、とんでもない爆弾です。
二度と、世界で核兵器が使われることがあってはいけないし、戦争をしてはいけないと思います」
みたいな、ペラっとした作文をテキトーに書いていました。
確か、社会科の授業だったか…
あるいは、今でいう「ゆとりの時間」みたいな時間帯だったかもしれない。
とにかくそういう内容で書いておけば及第点ですからね。
で、問題は、そんなふうに結論のわかりきった、
予定調和の平和学習は、退屈だということです。
この「虹の会」に参加した若い子たちは、
なんで人々がそんな悲惨な目にあったのかが知りたいというんですね。
この、若い子たちが考えたがっているという事実を、筆者はちょっと驚きをもって書いています。
若い子たちは、というか、こういう活動に能動的に参加するような若い子たちは、
一人ひとりの戦争体験の背後にある、大きな流れについて知りたがり、
考えたがっているのかな、と私も思いました。
学校で、近代史、現代史をロクに教えないことで、
(多少は教える側の主観が混じるけど、できるだけ)客観的に自国のあゆみを知ることが抜けている私たち。
(いや、私は今の子たちよりは年くってるけどさ、戦後教育という意味では同じカテゴリーじゃないかな)
だからこそ、ほんの60年前に起きたことを、
現在の自分たちの生活に結びつけて考えられないんじゃないかな。
で、私が「…そうだよね」と納得しながら読んだのは、
その虹の会のメンバーの一人が、ひめゆりだったけど、学徒動員には参加せず、
疎開して生き残った人たち、つまり、
自由意志で戦場に行かなかった人たちのことを知りたいと言ったところ。
でもそれは、ひめゆりOGたちの中でも、タブーの話題だったみたい。
戦場を生き抜いた人は、自分だけが生き残って友達に申し訳なく思う、というならば、
最初から戦場に行かなかった人は、一体ひめゆり学徒のことを、
あるいは学徒動員そのものを、どう思っているのか。
…それ、私も知りたいです。
「行かないという選択肢を選んだ人」に、話を聞いてみたい。
その子は、それを卒論のテーマにしたんだって。
…やるなあ!
もちろん、本全体で興味深いのは、
最初は、ひめゆりOGの言葉がこころに届かないと言ってた子たちが、
少しずつ、ひめゆりたちに当時の話を聞くことで、
60年前に同じ年代だった子の話として共感を覚えるようになり、
自らいろいろなことを考え始めた、その成長の過程です。
私自身、戦争を知らない世代だけど、
「戦争を知らない世代に、戦争のことを語る」ことが、
どうしても、テニアン本のコンテンツの一つになっちゃうだろうな、
と思っているので、そういう意味でも、ヒジョーに共感したり、
「ちっ。青春の甘えん坊だ、おまいの言ってることは」などとツッコミを入れたりしながら
とても興味深く読みました。
この本は、学校の先生に読んでほしいと思います。
そして、一人でも多くの先生が、ペラっとした平和学習を
生きたものに変えてくれたらいいなと思う。
広島・長崎そして沖縄の、地域限定かもしれないけど。
また、平和学習らしい機会のない地域の先生たちは、
自分たちの足もとで、戦争中何があったのかを学習する機会を、
何とかして作ってほしいと思います。
私の長女は5年生。だけど、東京大空襲のことは、まだ勉強してないみたい。
でも、地域の児童館では、毎年夏休みになると、
戦争被害関係のビデオ(おこりじぞうなどのこども向け作品ね)を見て、
地域のお年寄りと一緒にすいとんを作って食べる学習会が開かれています。
もしかしたら、学校では何も勉強しないのかもしれないな。。。
今年の夏休みは、広島の平和資料館を見に行ったけど、
ごった返しててゆっくり見られなかったから、
また原爆のことは機会を改めて、一緒に学ぶ機会を作らねばなるまい。
ひめゆりの人たちと、沖縄の高校生・大学生たちが、
一緒にこのテーマに取り組んだ「虹の会」の活動を紹介した本です。
色々な示唆に富んでいて、とても面白かった。
まず、平和学習について。
沖縄では小学生から高校生まで、6月23日の前になると、
平和学習という授業が行われるそうです。
沖縄戦の被害を語る講演やビデオを見て、その感想文を書くという内容が定番。
この平和学習は、小学校2年生から高校生まで、
ずっと同じレベルの学習をするのと同じようなものだ、
という指摘が、若者からありました。
算数なら、足し算、引き算、からどんどんレベルアップしていくのに、
平和学習でやることは、ずっと計算問題ばかり、というのと同じだというんですね。
確かに、「平和学習」の感想文で、「正解」として求められているのは、
「戦争は悲惨です。今日は命の大切さと平和の大切さを感じました。二度と戦争を起こしてはいけません」
という内容ですわな。
かく言う私も、小学校、中学校と、原爆のことを勉強するたびに、
「戦争は悲惨です。特に原爆は、罪もない人を簡単に殺し、後遺症で苦しめる、とんでもない爆弾です。
二度と、世界で核兵器が使われることがあってはいけないし、戦争をしてはいけないと思います」
みたいな、ペラっとした作文をテキトーに書いていました。
確か、社会科の授業だったか…
あるいは、今でいう「ゆとりの時間」みたいな時間帯だったかもしれない。
とにかくそういう内容で書いておけば及第点ですからね。
で、問題は、そんなふうに結論のわかりきった、
予定調和の平和学習は、退屈だということです。
この「虹の会」に参加した若い子たちは、
なんで人々がそんな悲惨な目にあったのかが知りたいというんですね。
この、若い子たちが考えたがっているという事実を、筆者はちょっと驚きをもって書いています。
若い子たちは、というか、こういう活動に能動的に参加するような若い子たちは、
一人ひとりの戦争体験の背後にある、大きな流れについて知りたがり、
考えたがっているのかな、と私も思いました。
学校で、近代史、現代史をロクに教えないことで、
(多少は教える側の主観が混じるけど、できるだけ)客観的に自国のあゆみを知ることが抜けている私たち。
(いや、私は今の子たちよりは年くってるけどさ、戦後教育という意味では同じカテゴリーじゃないかな)
だからこそ、ほんの60年前に起きたことを、
現在の自分たちの生活に結びつけて考えられないんじゃないかな。
で、私が「…そうだよね」と納得しながら読んだのは、
その虹の会のメンバーの一人が、ひめゆりだったけど、学徒動員には参加せず、
疎開して生き残った人たち、つまり、
自由意志で戦場に行かなかった人たちのことを知りたいと言ったところ。
でもそれは、ひめゆりOGたちの中でも、タブーの話題だったみたい。
戦場を生き抜いた人は、自分だけが生き残って友達に申し訳なく思う、というならば、
最初から戦場に行かなかった人は、一体ひめゆり学徒のことを、
あるいは学徒動員そのものを、どう思っているのか。
…それ、私も知りたいです。
「行かないという選択肢を選んだ人」に、話を聞いてみたい。
その子は、それを卒論のテーマにしたんだって。
…やるなあ!
もちろん、本全体で興味深いのは、
最初は、ひめゆりOGの言葉がこころに届かないと言ってた子たちが、
少しずつ、ひめゆりたちに当時の話を聞くことで、
60年前に同じ年代だった子の話として共感を覚えるようになり、
自らいろいろなことを考え始めた、その成長の過程です。
私自身、戦争を知らない世代だけど、
「戦争を知らない世代に、戦争のことを語る」ことが、
どうしても、テニアン本のコンテンツの一つになっちゃうだろうな、
と思っているので、そういう意味でも、ヒジョーに共感したり、
「ちっ。青春の甘えん坊だ、おまいの言ってることは」などとツッコミを入れたりしながら
とても興味深く読みました。
この本は、学校の先生に読んでほしいと思います。
そして、一人でも多くの先生が、ペラっとした平和学習を
生きたものに変えてくれたらいいなと思う。
広島・長崎そして沖縄の、地域限定かもしれないけど。
また、平和学習らしい機会のない地域の先生たちは、
自分たちの足もとで、戦争中何があったのかを学習する機会を、
何とかして作ってほしいと思います。
私の長女は5年生。だけど、東京大空襲のことは、まだ勉強してないみたい。
でも、地域の児童館では、毎年夏休みになると、
戦争被害関係のビデオ(おこりじぞうなどのこども向け作品ね)を見て、
地域のお年寄りと一緒にすいとんを作って食べる学習会が開かれています。
もしかしたら、学校では何も勉強しないのかもしれないな。。。
今年の夏休みは、広島の平和資料館を見に行ったけど、
ごった返しててゆっくり見られなかったから、
また原爆のことは機会を改めて、一緒に学ぶ機会を作らねばなるまい。
Posted by いのうえちず。 at 00:44
│沖縄
この記事へのコメント
沖縄での唯一の悔いは、平和公園にいけなかったこと。沖縄移住のために、去年の夏長崎原爆・軍艦島~広島原爆~神戸震災・で、冬の青森・恐山っと。。。一人旅をした。感覚で感じるウチは、旅行先の土地でいろいろかんじた。で、沖縄では。。。残念ながら時間 日なくいけず。。。偶然にも、父の書斎に「水筒」っという一冊の本を見つけた、漫画ながらも胸にぐっとひびいた。戦争をしらない、平和な今にいながら、平和のありがたさも、築いてきた大変さも忘れがちになってしまう。一人旅でのことを思い出し、すこしでも、学び知って生きて行きたい。
Posted by 凛祢 at 2006年10月22日 23:42
軍艦島行ったの!? いいな~。いいな~。
私、廃墟好きなので、早いうちに一度行きたい場所のひとつですよ。
色々な場所を旅して、色々なことを自分で感じ取るのは大事。
良い経験をされてきたのね。
平和な時代(といっても、世界には常に戦地がある)に生きる私たちには、平和のありがたさなんて、それを積極的に感じようとしなければ、ピンとこないのが当たり前だと思います。
当たり前でいいかどうかは、また別の話。
私、廃墟好きなので、早いうちに一度行きたい場所のひとつですよ。
色々な場所を旅して、色々なことを自分で感じ取るのは大事。
良い経験をされてきたのね。
平和な時代(といっても、世界には常に戦地がある)に生きる私たちには、平和のありがたさなんて、それを積極的に感じようとしなければ、ピンとこないのが当たり前だと思います。
当たり前でいいかどうかは、また別の話。
Posted by ちず。 at 2006年10月23日 11:02
ちずちゃん、廃墟マニアなの?
知り合いの廃墟マニアは、冬季分校マニアでもあるな。
実りある平和学習を目指すなら、【ラマダン(断食)】をすすめるね。
体験しないとありがたみなんてわからないよ。
知り合いの廃墟マニアは、冬季分校マニアでもあるな。
実りある平和学習を目指すなら、【ラマダン(断食)】をすすめるね。
体験しないとありがたみなんてわからないよ。
Posted by しっぽ♪ at 2006年10月23日 14:00
ちずさん、ただいま。
戦争すりゃいいなんてクソガキは現・地球の激戦地へ空輸しちゃえ!
帰ってきましたのでご挨拶でした。
戦争すりゃいいなんてクソガキは現・地球の激戦地へ空輸しちゃえ!
帰ってきましたのでご挨拶でした。
Posted by 南島中毒 at 2006年10月23日 23:50
いやー、日本みたいに温暖な国に住んでると、
砂漠の民の厳しい環境から生まれたものはまさに異文化であるね。>しっぽ♪さん
おかえり&おつかれさま。
そのクソガキ、実は物議を醸す目的で、
そんな発言を仕掛けていたのだよ。>南島中毒さん
砂漠の民の厳しい環境から生まれたものはまさに異文化であるね。>しっぽ♪さん
おかえり&おつかれさま。
そのクソガキ、実は物議を醸す目的で、
そんな発言を仕掛けていたのだよ。>南島中毒さん
Posted by ちず。 at 2006年10月24日 07:45
この本読んでみた~い。
学徒隊に出陣しなくて、疎開した人をモデルに書いた話読んだことある。(私が読んだのはマンガ)
その話の主人公は、結局疎開したけど、家族一緒に戦争に巻き込まれて行って自分は助かったんだけど、集団自決の傷をひきずり、学徒隊で出陣したみんなにも負い目があって、そのことをその後身内の誰にもいえず、沖縄に来られなかったというおばあちゃんでした。
原作あるなら読みたいんだけど、ちずちゃん知らない?
学徒隊に出陣しなくて、疎開した人をモデルに書いた話読んだことある。(私が読んだのはマンガ)
その話の主人公は、結局疎開したけど、家族一緒に戦争に巻き込まれて行って自分は助かったんだけど、集団自決の傷をひきずり、学徒隊で出陣したみんなにも負い目があって、そのことをその後身内の誰にもいえず、沖縄に来られなかったというおばあちゃんでした。
原作あるなら読みたいんだけど、ちずちゃん知らない?
Posted by さとちゃん at 2006年10月24日 23:38
本、送ろうか。しに面白かったよ。
そのマンガの原作は知らんなあ。
っつーか、その設定はなんだかリアルだなー。
「戦地に行かなかったひめゆり」
いいドキュメンタリーが撮れそうなテーマだと思うわ。
そのマンガの原作は知らんなあ。
っつーか、その設定はなんだかリアルだなー。
「戦地に行かなかったひめゆり」
いいドキュメンタリーが撮れそうなテーマだと思うわ。
Posted by ちず。 at 2006年10月25日 00:09
「沖縄ナビ」を読み、ちずさんのブログを見て、沖縄戦に興味を持つようになった私ですが、
一方で、自分の生まれ育った場所についてよくわかっていない自分の状況も、何とかしなくちゃならない気がしています。
岡山でも空襲があって、駅のそばを流れる西川にはたくさんの死体が浮かんだという話を聞いたのは、小学生の頃。
通った中学校は、陸軍の師団があったところ。
高校生以降、その内容は更新されていないようです。
実は私、高校の教員をしています。
ちずさんの言葉、自分なりに受け止めて、何ができるか考えようと思います。
一方で、自分の生まれ育った場所についてよくわかっていない自分の状況も、何とかしなくちゃならない気がしています。
岡山でも空襲があって、駅のそばを流れる西川にはたくさんの死体が浮かんだという話を聞いたのは、小学生の頃。
通った中学校は、陸軍の師団があったところ。
高校生以降、その内容は更新されていないようです。
実は私、高校の教員をしています。
ちずさんの言葉、自分なりに受け止めて、何ができるか考えようと思います。
Posted by Kawaiea at 2006年10月25日 01:59
うわ!先生だったのか!
>何ができるか考えようと思います。
これ、素直にうれしいです!!
>何ができるか考えようと思います。
これ、素直にうれしいです!!
Posted by ちず。 at 2006年10月25日 07:31
本を読みました。
「ひめゆり時代は自由で民主的だった」というけれど、それは小学生で軍国教育を受けていたからだ、というのが私にとっては目からウロコでした。
ひめゆりの人たちも、青春を謳歌する10代後半の乙女である(はずだった)ことにも、改めて気づかされました。
戦争により大変な苦難の道を歩んだ人たちも、本来今の人と何ら変わりはなかった。
戦争教育を考える上で、少し実感というか、いとぐちが見える気がしました。
この本にもちらっと書かれていましたが、現場では、「人権教育」に重きが置かれているようで、「平和教育」というのは、なかなか導入しづらいと思います。
修学旅行前の事前学習なら可能かも。
その延長上に、身近なところに目を向けさせる活動があれば…。
それにしても、
この本、すぐに読みたいと思って1日で7件本屋を回ったものの、どこにもありませんでした。
翌日県立図書館に行くと、ありましたので、
借りて読んだ次第です。
(水木しげるのラバウル戦記・戦火と死の島に生きるも同時に)
売れ筋でなければ、発売数ヶ月の本でも店頭に並ばないというのは、困ったものだと。
あ、「沖縄ナビ」「沖縄スタイル」はどこの本屋にもありましたよ。
もちろん、図書館にも。
「ひめゆり時代は自由で民主的だった」というけれど、それは小学生で軍国教育を受けていたからだ、というのが私にとっては目からウロコでした。
ひめゆりの人たちも、青春を謳歌する10代後半の乙女である(はずだった)ことにも、改めて気づかされました。
戦争により大変な苦難の道を歩んだ人たちも、本来今の人と何ら変わりはなかった。
戦争教育を考える上で、少し実感というか、いとぐちが見える気がしました。
この本にもちらっと書かれていましたが、現場では、「人権教育」に重きが置かれているようで、「平和教育」というのは、なかなか導入しづらいと思います。
修学旅行前の事前学習なら可能かも。
その延長上に、身近なところに目を向けさせる活動があれば…。
それにしても、
この本、すぐに読みたいと思って1日で7件本屋を回ったものの、どこにもありませんでした。
翌日県立図書館に行くと、ありましたので、
借りて読んだ次第です。
(水木しげるのラバウル戦記・戦火と死の島に生きるも同時に)
売れ筋でなければ、発売数ヶ月の本でも店頭に並ばないというのは、困ったものだと。
あ、「沖縄ナビ」「沖縄スタイル」はどこの本屋にもありましたよ。
もちろん、図書館にも。
Posted by Kawaiea@出張先 at 2006年11月09日 00:37
Kawaieaさん、出張先からのカキコありがとう。
小学生で軍国教育を受けていたからだっていうので目からウロコってさ、
あたしゃ陸軍中野学校関連の書籍で「はっ!」と同じ思いだったよ!
たまたま、この「ひめゆり」より「陸軍中野学校」の本を読んだのが先だったから。
もし、この「ひめゆり」が先だったら、全く同じ感想を持ってたはず。
陸軍中野学校は、いわゆるスパイ養成校だったんだけど、
天皇制について議論するなど、
当時の社会情勢からは考えられないと私たちが思い込んでいたことが、
(機密の中では)堂々と行われていたって記述が、
複数の書籍にあったわけよ。
軍国教育を受けていることが前提だというのが、
全然、実感としてわかってなかったから、
「陸軍の中でも生粋の右だろう」と思ってたのね。
でも実際は、かなりリベラル?と思われる発言も許容範囲内だった。
信念として国を(時には狂信的に)愛したとしても、
冷静さを伴わなければ、工作だの諜報だので、
プロの仕事はできないわけで。
まして海外でそういう仕事をする場合、
自分の中で論理的に納得ができていなければ、
誠意をもって諜報活動なんかできないもん。
いばりくさった憲兵のイメージ、沖縄県民を殺す日本兵のイメージ、
大陸で虐殺と強姦をしてきた日本兵のイメージが強烈で、
一人の人間として、想像することができなかったのか?
あるいは、「特務=狂信的」という思い込みがあったのか?
昨日、たまたま見かけたおじいさんのケツが筋肉質で、
「昔、鍛えたのかな~」と漠然と思った時、
「元軍人さんかも?」と、実際には見たこともない軍服の後姿が重なってリアルにイメージできて、なんだか不思議な気持ちになりました。
そーか、人権教育か。なるほど。
平和教育、平和学習って名前も、あんまし良くないのかね?
加害と被害の両面から見る「戦争学習」でいいと思うが、
文字面が左翼の人から嫌われそうだな。
水木しげるの本、面白いよ~。
かっこよく、美しく書かれた戦記ものにはないリアリティがある。
沖ナビ、書店にあったのかぁ。うれしいな~。
小学生で軍国教育を受けていたからだっていうので目からウロコってさ、
あたしゃ陸軍中野学校関連の書籍で「はっ!」と同じ思いだったよ!
たまたま、この「ひめゆり」より「陸軍中野学校」の本を読んだのが先だったから。
もし、この「ひめゆり」が先だったら、全く同じ感想を持ってたはず。
陸軍中野学校は、いわゆるスパイ養成校だったんだけど、
天皇制について議論するなど、
当時の社会情勢からは考えられないと私たちが思い込んでいたことが、
(機密の中では)堂々と行われていたって記述が、
複数の書籍にあったわけよ。
軍国教育を受けていることが前提だというのが、
全然、実感としてわかってなかったから、
「陸軍の中でも生粋の右だろう」と思ってたのね。
でも実際は、かなりリベラル?と思われる発言も許容範囲内だった。
信念として国を(時には狂信的に)愛したとしても、
冷静さを伴わなければ、工作だの諜報だので、
プロの仕事はできないわけで。
まして海外でそういう仕事をする場合、
自分の中で論理的に納得ができていなければ、
誠意をもって諜報活動なんかできないもん。
いばりくさった憲兵のイメージ、沖縄県民を殺す日本兵のイメージ、
大陸で虐殺と強姦をしてきた日本兵のイメージが強烈で、
一人の人間として、想像することができなかったのか?
あるいは、「特務=狂信的」という思い込みがあったのか?
昨日、たまたま見かけたおじいさんのケツが筋肉質で、
「昔、鍛えたのかな~」と漠然と思った時、
「元軍人さんかも?」と、実際には見たこともない軍服の後姿が重なってリアルにイメージできて、なんだか不思議な気持ちになりました。
そーか、人権教育か。なるほど。
平和教育、平和学習って名前も、あんまし良くないのかね?
加害と被害の両面から見る「戦争学習」でいいと思うが、
文字面が左翼の人から嫌われそうだな。
水木しげるの本、面白いよ~。
かっこよく、美しく書かれた戦記ものにはないリアリティがある。
沖ナビ、書店にあったのかぁ。うれしいな~。
Posted by ちず。 at 2006年11月09日 10:22