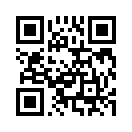2009年01月12日
働くくるま
南大東島は、サトウキビの島。
製糖期に行くと、こんな風景に出会いますぜ。

3台1セットで働くよん。
製糖期に行くと、こんな風景に出会いますぜ。
3台1セットで働くよん。
ハーベスターが入る下準備をするクルマ(名称わからん)と、
ハーベスターと、収穫したキビを運搬するトラック。

チームワークもよく、仲良しトリオに見えました。
運搬車はとっても車高が高い!
ハーベスターの高さに合わせてるんだって。
1台の荷台がいっぱいになると、次のトラックがすかさず交代するよん。
どんどん出てこい♪はたらくクルマ~♪
なんだか沖縄じゃないみたいな光景だ。
ハーベスターの導入には、実は南大東島の近・現代史が大きく関わってます。
八丈島系の移民が多かったことで知られる南大東島。
島は製糖会社の天下。ハッキリとしたヒエラルキーがあったといいます。
頂点は、製糖会社のトップである内地人、次に八丈人、
うちなーんちゅは、八丈島の下に置かれていました。
小作人というか、出稼ぎの労務者みたいな立場の人が多かった、と。
戦時中、退島命令が出たとき、真っ先に疎開したのは内地人。
次に、経済力のあった八丈島の人。
貧しいうちなーんちゅの多くは、島に残った。
戦後の南大東はアメリカ領になった。出て行った人たちは戻ってこなかった。
となると、単純に、労働力が足りない。
製糖期だけ、労働者を雇うことになる。
勤勉で甘蔗栽培の経験が豊富な台湾人は最適だった。
でも日中国交正常化の影響で、気軽に行き来できなくなった。
しょうがないので韓国人を雇った。
やってきた人たちは勤勉とは言えず、何かとサボろうとするので雇うのはやめた。
宮古の人たちを雇ったこともあった。
勤勉ではあったけど、キセツで来た人は気の荒い人が多かったためか
夜の街で諍いが絶えなかったとか。
結局、人力に頼らず、機械化を進めることになった。
オーストラリアに視察に行ったり、海外の事例を参考にしたそうな。
農家一戸あたりの経営耕作面積は約7ヘクタールと広い。
機械化にあたり、傾斜地を平坦にすべく地形を変えたところも少なくないそうな。
高額なハーベスターを導入するには、ある程度の規模は必要だよな~。

最初はのんきに
「うわー、ハーベスターでかっ!強力!かっけー!」
と、表面的な反応をしてしまいましたが、
そういう話を聞くと、
「ふーむ、すべての物事には原因があって、結果があるのだなあ」
と、仏教徒らしい反応を示してしまいます。
ハーベスターと、収穫したキビを運搬するトラック。
チームワークもよく、仲良しトリオに見えました。
運搬車はとっても車高が高い!
ハーベスターの高さに合わせてるんだって。
1台の荷台がいっぱいになると、次のトラックがすかさず交代するよん。
どんどん出てこい♪はたらくクルマ~♪
なんだか沖縄じゃないみたいな光景だ。
ハーベスターの導入には、実は南大東島の近・現代史が大きく関わってます。
八丈島系の移民が多かったことで知られる南大東島。
島は製糖会社の天下。ハッキリとしたヒエラルキーがあったといいます。
頂点は、製糖会社のトップである内地人、次に八丈人、
うちなーんちゅは、八丈島の下に置かれていました。
小作人というか、出稼ぎの労務者みたいな立場の人が多かった、と。
戦時中、退島命令が出たとき、真っ先に疎開したのは内地人。
次に、経済力のあった八丈島の人。
貧しいうちなーんちゅの多くは、島に残った。
戦後の南大東はアメリカ領になった。出て行った人たちは戻ってこなかった。
となると、単純に、労働力が足りない。
製糖期だけ、労働者を雇うことになる。
勤勉で甘蔗栽培の経験が豊富な台湾人は最適だった。
でも日中国交正常化の影響で、気軽に行き来できなくなった。
しょうがないので韓国人を雇った。
やってきた人たちは勤勉とは言えず、何かとサボろうとするので雇うのはやめた。
宮古の人たちを雇ったこともあった。
勤勉ではあったけど、キセツで来た人は気の荒い人が多かったためか
夜の街で諍いが絶えなかったとか。
結局、人力に頼らず、機械化を進めることになった。
オーストラリアに視察に行ったり、海外の事例を参考にしたそうな。
農家一戸あたりの経営耕作面積は約7ヘクタールと広い。
機械化にあたり、傾斜地を平坦にすべく地形を変えたところも少なくないそうな。
高額なハーベスターを導入するには、ある程度の規模は必要だよな~。
最初はのんきに
「うわー、ハーベスターでかっ!強力!かっけー!」
と、表面的な反応をしてしまいましたが、
そういう話を聞くと、
「ふーむ、すべての物事には原因があって、結果があるのだなあ」
と、仏教徒らしい反応を示してしまいます。
Posted by いのうえちず。 at 04:29
│沖縄
この記事へのコメント
中古車・中古トラックを買う前にまずは一度のぞいてみて下さい。お得な情報があるかも知れません。
Posted by トラックの役に立つ情報 at 2009年03月30日 13:15